私が使用している暦に、「亥の子餅」と書いてあって・・・
亥の子は主に関西地方に伝わる行事で、関東以北にお住まいの方にはあまり馴染みのない行事かも・・・
青森では聞いたことがなかったです。
古代中国において行われていた「亥子祝」という行事が、
平安時代に伝わって定着したものという説が多いようです。
当時は宮中の年間行事で行われていました。
旧暦の10月は亥の月です。
亥の月の最初の亥の日、亥の刻(21時~23時)に「亥の子祝い」が行われていました。
「亥の子祝い」とは、子供をたくさん産むイノシシにあやかって、
亥の子餅やイノシシのお菓子(和三盆)などを食べて子孫繁栄や収穫祝い、
無病息災を祈る祭りです。
また、亥が火に強いことから、
この日にこたつ開きや炉開きをすると火災を逃れられると言われているそうです。
そろそろこたつや暖房器具を出そうかと考えている人は、亥の日に出してもいいですね。
亥の子餅とは、亥の子=イノシシの子ども、つまりウリ坊に見立てたお餅のこと。
古くは、その年に収穫された大豆・小豆・ささげ・ごま・栗・柿・糖(あめ)の
7種の粉を新米に入れて作っていました。
最近では、亥の子餅は10月〜11月にかけて、和菓子店などに並びます。
店によって材料や見た目が異なるので、デパ地下など回って好みの1品を見つけるのも良いですね。
「亥の月、亥の日、亥の刻に亥の子餅を食べると病気にならない」という言い伝えもあるそうです。
亥の子の日に、こたつなどの暖房器具を出し、無病息災や子孫繁栄を祈って
亥の子餅をいただいてみましょ♪
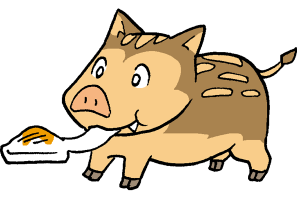
寒露初候
第四十九候「鴻雁来(こうがんきたる) 」新暦10月8日〜10月12日 頃
北から雁が帰ってくる
植物 しめじ、ななかまど
魚 柳葉魚(ししゃも)
動物
行事など ⻑崎くんち
⻑崎の諏訪大社で旧暦の9月9日に行われる。
ななかまどは7回竃に入れても焼き切れない生命力を持つといわれる。
ケルトの守護樹にも選ばれている。(花言葉は慎重・思慮分別・解毒力慈悲)
暦を生活に取り入れるようになり、季節を感じるようになりました。
旬のものを見たり食べたり生活に取り入れて見ませんか?
暦と旅の案内人「こよみすと」ワンデイ講座を学び、こよみ生活はじめましょ♪
お申し込みはこちらへ






















この記事へのコメントはありません。