暦の上では、夏の始まりですね。
そして5月5日「こどもの日」といえば、鯉のぼりや柏餅・ちまき、菖蒲湯など浮かびますが、
どうですか?
こどもの日に、香りで邪気を払う・無病息災をからと菖蒲湯に入っていたのですが…
中国ではもともと端午、つまり5月ごろ、菖蒲を玄関に飾ることで邪気を払う風習があり、
また同時期には、蘭を浮かべた蘭湯に入り身を清める“浴蘭節”も行われていて、
二つの風習が伝わりました。
旧暦の5月は伝染病の流行や害虫被害などが多く、古代中国の人々は邪気払いのために
蘭湯に入ったといいます。
日本には肝心の蘭草が少ないという問題があり、代用となったのが、菖蒲だったんです!
葉の形が剣に似ていることからたくましい男の子に成長してほしい!
という願いが込められるようになり、
武士が出陣前に菖蒲湯に浸かり、無事を祈願した、という説もあるようです。
菖蒲にはテルペンやアザロン、オイゲノールといった成分が含まれています。
これらの成分が疲労回復・精神安定・リラックス効果・血行促進・冷え性や肩こりなどの
効果が期待できます。
菖蒲湯に入れない方は、その他の方法で香りだけでも楽しんでみませんか!
5月4日の夜、菖蒲とヨモギを束ね、枕の下に敷いて寝る「菖蒲枕」 。
これは菖蒲の強い香りでもって、邪気を払おうとするもの。
菖蒲の根(茎や葉で代用)を刻み、30分ほどお酒に浸せば「菖蒲酒」の完成。
こちらは解毒効果や殺菌効果が期待できるそうですよ♪
お子さんや妊婦さんは、お酒をお水に変えてくださいね。
使用後の菖蒲を乾燥させれば芳香剤や虫よけにできるとか…
菖蒲を入浴以外にも利用してみましょ♪

立夏初候
第十九候「鼃始鳴(かわずはじめてなく)」 新暦5月5日〜5月9日 頃
田畑でカエルが鳴きはじめる
植物 人参(にんじん)
藤(ふじ)、柏(かしわ)
魚 金目鯛(きんめだい)
動物 蛙(かえる)、時鳥(ほととぎす)
行事など 端午の節句: 邪気祓いに菖蒲湯に入り、柏餅を食べる。
藤の花は春と夏にまたがって花咲くことから、別名「二季草」と呼ばれる。(花言葉は、王者の風格・富貴・ 誠実)
柏は新芽が出るまで葉が落ちないので家系が絶えない縁起もの。 (花言葉は、勇敢・独立・自由)
人参(にんじん)は栄養豊富で免疫力を高める。(花言葉は、幼い夢)
暦を生活に取り入れるようになり、季節を感じるようになりました。
旬のものを見たり食べたり生活に取り入れて見ませんか?




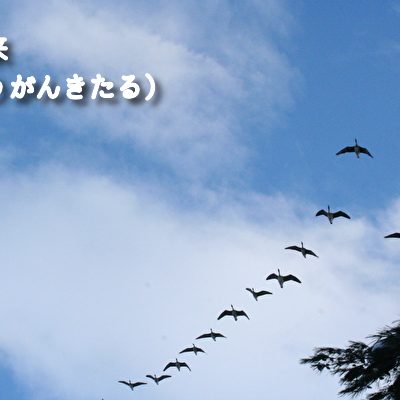
















この記事へのコメントはありません。